ジャガイモの収穫の後、さつまいもを植える時期がくるけれど、芋同士は連作になる?他にはどんな物がダメなのか?そもそも連作障害とは何か、それがなぜ問題とされるのかを理解することで、効果的な農業を営む事ができます。この記事では、ジャガイモの連作障害の基本からその対策までを初心者にもわかりやすく説明します。
ジャガイモ収穫時期
5月末から6月あたりにじゃがいもの収穫時期がきますね。ジャガイモの収穫時期は、植えた品種や気候、栽培目的によって異なりますが、一般的なガイドラインとして以下のようなポイントが挙げられます。
ジャガイモの品種による分類
ジャガイモはその成熟期によって「早生品種」「中生品種」「晩生品種」に大別されます。
早生品種: 植付けから約90日で収穫可能です。春に植えると初夏に収穫できるため、気候が温暖な地域で好まれます。
中生品種: 植付けから約120日で収穫可能です。一般的に最も多く栽培されるタイプで、夏の終わりに収穫されます。
晩生品種: 植付けから150日以上かかり、主に貯蔵用として栽培されます。晩秋に収穫されることが多いです。
収穫のタイミング

ジャガイモの収穫時期は、葉が黄色く枯れ始め、茎が倒れることが目安とされます。この時期になると、ジャガイモの皮が堅くなり始め、地中での保存に適した状態になります。収穫が早すぎると、皮が薄く、傷つきやすいため、貯蔵には不向きです。
地中のジャガイモをチェック: 収穫前に地中のジャガイモを掘り起こして確認し、皮が十分に堅くなっているかを確認します。手で軽くこすっても皮が剥がれない状態が理想的です。
収穫の方法

収穫は
- 土が乾燥している日を選ぶ
- ジャガイモが土中にしっかりと根を張るまで待つこと
が重要です。
フォークや専用の収穫機を使って、植物を傷つけないように注意しながら掘り起こします。ジャガイモが露出したら、土から取り除き、乾燥させてから保管します。
収穫後の処理

収穫後、ジャガイモは日陰で数時間から一日程度乾燥させることが一般的です。これにより土が落ちやすくなり、皮が硬化して貯蔵時の耐久性が向上します。その後、涼しく乾燥した場所に保管することで、数ヶ月間保存することができます。
ジャガイモの収穫時期と方法は、最終的には地域の気候や土壌の状態、目的によって左右されるので個人差があります。
じゃがいものサイズ別味や栄養の違い

ジャガイモは、小さな新じゃがから大きな成熟したものまで、さまざまなサイズで収穫されますが、その大きさが味や使い勝手、栄養内容に与える影響を理解することは料理をする上で役立ちます。
- でんぷん質が多く含まれている
- 食感がほくほく
- マッシュポテトやベイクドポテトに適している
- ビタミンC、ビタミンB6、カリウム、マグネシウムなどが豊富 一食分のカロリー高め
- でんぷん質が少なく、水分が多い
- 皮が薄くて柔らかいため、皮ごと調理して楽しむことができます。
- 味が甘く、しっとりとした食感
- サラダや煮物
- ビタミンCが豊富で、特に皮近くに栄養が集中しているため、皮付きでの調理が推奨されます。
連作障害の基本:ジャガイモ栽培の隠れたリスク
ジャガイモを同じ土地で続けて栽培すると、特定の病気や害虫が増え、土壌の健康が損なわれることがあります。連作障害は、土壌の微生物のバランスが崩れることによって引き起こされるため、その影響は時として深刻になります。
ジャガイモの生産性低下の背後にある真実
ジャガイモの連作障害による最も一般的な問題は、生産性の低下です。例えば、土壌中の有害な菌や病原菌が増えることにより、ジャガイモの根がうまく成長できなくなります。また、土壌中の栄養素が枯渇することもあり、これが栄養不足を引き起こし、結果として小さくて質の低いジャガイモが収穫されることになるのです。
さらに、連作によって土壌が硬くなり、水はけが悪くなることもあります。これにより、ジャガイモの根が十分な水分を吸収できず、生育が阻害されることがあります。
連作障害の原因と対策:じゃがいもの後に避けるべき野菜
ジャガイモの連作障害が起きない為にも、次に植えてはいけない物から、どれくらい期間をあければいいのか等具体的にお伝えします。
ジャガイモの後に避けた方が良い野菜には、主にナス科の植物が含まれます。ジャガイモはナス科に属し、同じ科の植物を連続して栽培すると連作障害のリスクが高まります。以下は、ジャガイモの後に栽培を避けるべきナス科の野菜と、その理由を詳しく説明します。
ナス科の野菜

- トマト
- ナス
- ピーマン
- トウガラシ
これらの野菜はジャガイモと同じナス科に属しているため、同様の病害虫や土壌病原菌に感染するリスクがあります。具体的には、以下の病気が問題となることが多いです。
病害虫と病気
- べと病(Phytophthora infestans): ジャガイモやトマトに共通して影響を与える病気で、葉や茎、果実に被害をもたらします。
- 黒斑病(Alternaria solani): 主にジャガイモとトマトに影響する病気で、葉に黒い斑点が出現し、最終的には植物の生育を妨げます。
- 根こぶ病(Root-knot nematodes): ジャガイモやその他ナス科の作物の根にこぶを形成し、栄養の吸収を阻害します。
土壌消耗問題
ナス科の植物は栄養要求が高く、特にカリウムを多く消耗します。ジャガイモ栽培後の土壌では、これらの栄養が不足している可能性があります。そのため、同じ科の作物を連続して栽培すると、栄養不足により生育不良を引き起こすリスクがあります。
ジャガイモの後にサツマイモは植えてもいい理由

ジャガイモの後にサツマイモは同じ芋だから連作になるとおもわれがちですが、実はジャガイモとサツマイモは科が違いますのでジャガイモの後にさつまいもを植えることは、一般的には問題ないとされています。
- ジャガイモはナス科
- サツマイモはヒルガオ科
に分類されます。
このため、両者は異なる種類の病気や害虫に感染する傾向があり、直接的な病害のリスクが重なることは少ないです。しかし、連作障害の観点から土壌管理の方法に注意する必要があります。
土壌の健康
ジャガイモの栽培は、土壌から多くの栄養素を消耗するため、特にリン酸とカリウムの消耗が激しいとされています。さつまいもは窒素やリン酸なども比較的多く必要とするため、ジャガイモの後にさつまいもを植える場合は、土壌の栄養状態を事前に確認する必要があるかもしれません。
土壌改良と輪作
さつまいもの栽培前には土壌改良を行うことが推奨されます。有機質の追加、pH調整(5.5から6.5のやや酸性)に適切な肥料の施用は、土壌の健康を保ち、連作障害を防ぐのに役立ちます。
総じて、ジャガイモの後にさつまいもを植えることは可能ですが、土壌の栄養状態や病害虫の管理に注意し、適切な土壌改良を行うことが重要です。
じゃがいもの後に植えるのに適してる野菜
ジャガイモの後にナス科以外の野菜を選ぶことは、連作障害のリスクを軽減し、土壌の健康を維持するのに役立ちます。じゃがいもの後に植えるのに最も適している野菜は?
レギューム科(豆類)

- エンドウ豆
- そら豆
- グリーンビーンズ
これらの作物は、窒素固定能力があるため、土壌に窒素を添加し、次の作物の成長に必要な栄養を提供します。窒素は植物の成長に必須の要素であり、特に葉の成長を促進します。
アブラナ科

- カブ
- キャベツ
- ブロッコリー
アブラナ科の作物は、土壌の異なる病害虫に対する抵抗力があるため、ジャガイモの後に適しています。これらの作物はまた、土壌を改良する効果も持ち、硬くなった土をほぐしやすくします。
イネ科

- トウモロコシ
トウモロコシは高い生育力を持ち、ジャガイモとは異なる栄養要求があるため、ジャガイモの後に植えると良い選択肢です。また、トウモロコシは土壌の異なる病害虫に対する抵抗力があります。
その他の適した作物
- ホウレンソウ
- レタス
これらの葉物野菜は比較的短期間で収穫が可能で、連作障害のリスクを軽減します。さらに、これらは異なる種類の栄養素を土壌から消耗するため、ジャガイモとの輪作に適しています。
ジャガイモの後の作物選びにおいては、病害虫のリスクを避けるためにも植物科の多様性を考慮し、適切な作物ローテーションを計画することが重要です。
不耕起農法と耕起農法のメリットデメリット

無農薬や化成肥料を使用しない野菜栽培において、土壌の耕起(従来の耕作方法)と不耕起(ノーティル農法)の選択は、土壌の健康と微生物の活動に大きく影響します。それぞれの方法には利点と欠点がありますが、微生物を活かし、健康な野菜を育てる目的で考えると、不耕起の方が多くの利点があります。
不耕起農法の利点
不耕起農法は、土壌を耕さずにその構造をそのまま保持する方法です。この方法には以下のような利点があります:
土壌の生物多様性の保護: 土壌を耕すと、土壌中の微生物の生態系が乱され、特に菌類やその他の有益な微生物が損なわれることがあります。不耕起では、これらの微生物が自然な状態で活動を続けることができ、土壌の生物多様性が保たれます。
土壌の健康の改善: 土壌の上層部を保護することで、有機物の分解を助け、土壌の肥沃度を向上させます。また、土壌の水分保持能力が向上し、浸食が減少します。
病害虫のリスクの低減: 土壌の健康が向上することで、病害虫の発生が抑えられることがあります。土壌中の有益な微生物が病原菌の抑制を助けることもあります。
耕起農法の欠点
耕起農法は土壌を掘り返し、柔らかくすることが主な特徴ですが、次のような欠点があります:
土壌の乾燥と浸食の促進: 土壌を掘り返すことで、土壌が乾燥しやすくなり、水と栄養素が流出しやすくなります。これは特に雨が多い地域で問題となります。
微生物の生態系の破壊: 土壌を掘り返すと、微生物の生息層が乱れ、特に菌類のネットワークが断ち切られることがあります。
総合的な推奨
無農薬・無化成肥料での野菜栽培を目指す場合、不耕起農法は土壌の生物多様性を保護し、土壌の健康を長期的に維持するための良い選択肢です。土壌の微生物が健全な環境で活動できるようにし、それにより植物の健康と成長を支えることができます。
ただし、不耕起農法を成功させるには、土壌の表面にカバークロップや有機質のマルチ(枯葉や草など)を適用し、土壌を保護する工夫が必要です。この方法で、土壌の保水性や栄養状態を向上させ、元気な野菜を育てることができます。
じゃがいもを栽培中*無農薬化成肥料無しで育てた結果
私は、ジャガイモを植えてから一切の水もあげず、栽培中:無農薬・化成肥料無しのほっらたかし農法で育てましたが、見事に甘くておいしいじゃがいもができました。
大きさは大きいのから小粒まで様々でしたが、どの大きさもおいしくフライドポテトはホクホクで子供にも好評でした。

スーパーに売るには形や大きさがそろっていないといけない等があるかもしれません。ですが、今はもう大きさや形よりいかに自然の物であるのかが大事なのかなと感じています。
是非みなさんも家庭菜園でじゃがいもの栽培にチャレンジしてみてください☆彡
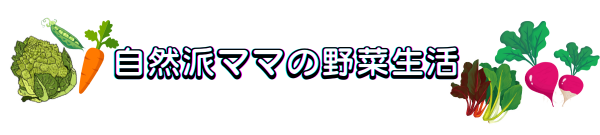


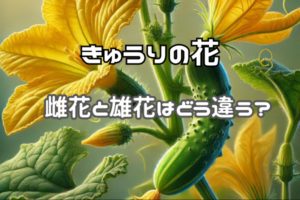


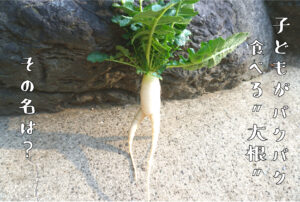

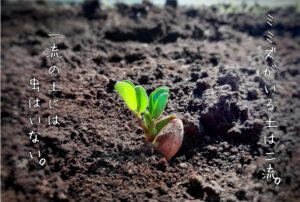
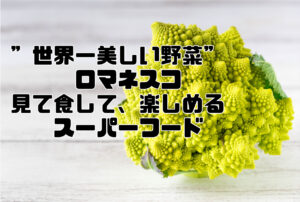
コメント